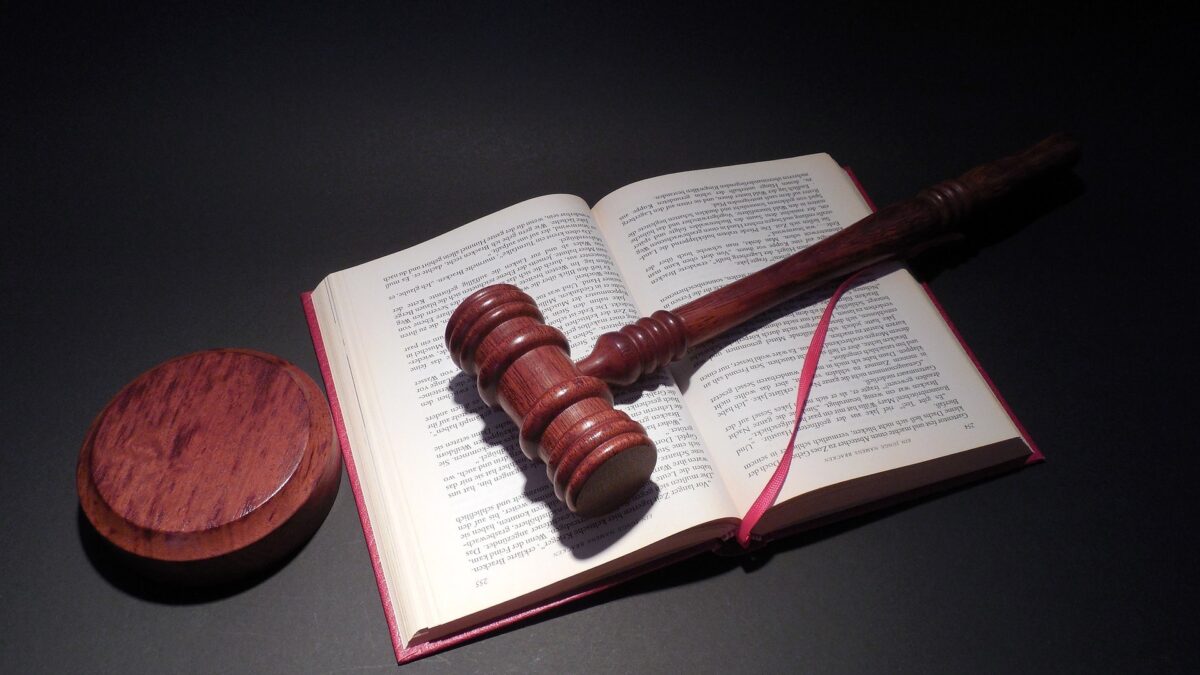「あの社員、もう限界だ…!でも、解雇したら訴えられるかもしれない…」
中小企業の社長にとって、問題社員の存在は頭痛の種です。しかし、安易な解雇は、訴訟リスクを高め、会社の存続を揺るがしかねません。
今回は、問題社員の解雇で会社を守るためのリスク回避術を、法的根拠から訴訟リスクまで、具体的な事例と心理描写を交えながら、徹底解説します。
目次
そもそも日本社会において解雇はあり?【法的根拠を徹底解説】
日本の法律では、従業員の解雇は厳しく制限されています。しかし、一定の要件を満たせば、解雇は認められます。
- 労働契約法第16条(解雇)
- 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
- つまり、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。
- 解雇の種類
- 普通解雇:労働者の能力不足や勤務態度不良などを理由とする解雇
- 整理解雇:会社の経営状況悪化などを理由とする解雇
- 懲戒解雇:労働者の重大な規律違反などを理由とする解雇
解雇が認められるケース
- 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合
- 労働者の能力不足や勤務態度不良が著しく、改善の見込みがない場合
- 会社の経営状況が著しく悪化し、人員削減が避けられない場合
- 労働者が重大な規律違反を犯し、懲戒解雇相当である場合
解雇が認められないケース
- 客観的に合理的な理由がない場合
- 社会通念上相当であると認められない場合
- 労働者の能力不足や勤務態度不良が軽微であり、改善の余地がある場合
- 会社の経営状況が安定しており、人員削減の必要性がない場合
- 労働者の規律違反が軽微であり、懲戒解雇が重すぎる場合
問題社員との向き合い方【感情的にならず、冷静に、丁寧に】
問題社員との対話は、感情的にならず、冷静かつ丁寧に行うことが重要です。
- 事実の確認
- 問題社員の言い分をよく聞き、事実関係を正確に把握する。
- 周囲の社員からの情報も収集し、客観的な視点を持つ。
- 改善の機会
- 問題点を具体的に指摘し、改善のための猶予期間を与える。
- 改善計画を作成し、定期的に進捗状況を確認する。
- 記録の作成
- 問題社員との面談内容、改善計画、進捗状況などを記録する。
- 記録は、日時、場所、参加者、内容などを詳細に記載する。
解雇せざるを得ない場合の注意点【手続きは慎重に、証拠は確実に】
改善の見込みがない場合、解雇もやむを得ません。しかし、解雇の手続きは慎重に行う必要があります。
- 解雇予告
- 解雇日の30日前に、解雇理由を明記した解雇予告通知書を交付する。
- 解雇予告手当を支払う場合は、解雇予告通知書に明記する。
- 解雇理由証明書
- 問題社員から請求があった場合、解雇理由証明書を交付する。
- 解雇理由証明書には、解雇理由を具体的に記載する。
- 弁護士への相談
- 解雇の手続きに不安がある場合は、弁護士に相談する。
●例:飲食店の場合
顧客への暴言や暴力行為が絶えない社員・Iさんを解雇した。解雇予告通知書と解雇理由証明書を交付し、解雇予告手当も支払った。Iさんは、解雇理由に納得せず、労働基準監督署に駆け込んだ。しかし、飲食店の経営者Kさんは、防犯カメラの映像や他の従業員の証言などを証拠として提出し、解雇の正当性を主張した。また、経営者Kさんは、Iさんに対して、過去に何度も注意や指導を行っていたことを記録した資料も提出した。
解雇後のリスク回避【訴訟に備える】
解雇後も、訴訟リスクは残ります。訴訟に備え、心の準備もしておきましょう。
- 弁護士との連携
- 訴訟に発展した場合に備え、弁護士と連携しておく。
- 弁護士に、解雇の経緯や証拠などを共有しておく。
- 心のケア
- 解雇は、経営者にとっても大きなストレスとなる。
- 信頼できる人に相談したり、カウンセリングを受けるなど、心のケアも忘れずに。
まとめ
問題社員の解雇は、経営者にとって大きな決断です。しかし、会社を守るために、最善を尽くす必要があります。